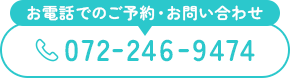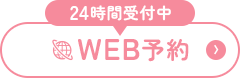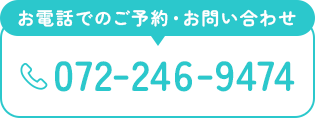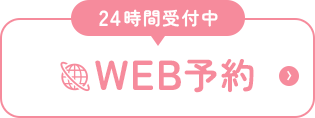- 子供が受け口じゃないのにしゃくれてる?
- 顎のしゃくれと受け口は別?2つの違いとは
- 顎のしゃくれ・受け口になる原因
- 子供は、わざと顎を前に出す
(しゃくれる)癖がある? - 子供の顎のしゃくれ・受け口を放置すると…
- 顎のしゃくれ・受け口(反対咬合)の治療法
子供が受け口じゃないのに
しゃくれてる?
 しゃくれは下顎が上顎を前方に越える状態で、噛み合わせの不具合や発音の問題、見た目へのコンプレックスに影響を及ぼすことがあります。これにより、多くの方が矯正治療を求めることがあります。
しゃくれは下顎が上顎を前方に越える状態で、噛み合わせの不具合や発音の問題、見た目へのコンプレックスに影響を及ぼすことがあります。これにより、多くの方が矯正治療を求めることがあります。
受け口は歯並びの問題から生じることが多く、しゃくれのように見えることがありますが、しゃくれには骨格の問題が原因のタイプもあり、外見上似ていても、根本の原因は異なります。
そのため、受け口としゃくれは同一ではなく、それぞれに適した治療法が存在します。このような状態は早期に専門家に相談し、適切な診断と治療計画を立てることが重要です。
顎のしゃくれと受け口は別?
2つの違いとは
 受け口は歯の配置に関連する問題で発生し、しゃくれは顎の骨格に起因する問題です。両者は下顎が前方に出るという共通点があるものの、原因となる要素が異なるため、それぞれ別の状態として扱われます。ここでは、それぞれの違いについて解説します。
受け口は歯の配置に関連する問題で発生し、しゃくれは顎の骨格に起因する問題です。両者は下顎が前方に出るという共通点があるものの、原因となる要素が異なるため、それぞれ別の状態として扱われます。ここでは、それぞれの違いについて解説します。
しゃくれの特徴
しゃくれは下顎が上顎より前に出ている顔の輪郭を指します。骨格の問題であり、必ずしも、受け口(歯並びの問題)を意味するわけではありません。下顎の骨が、下の歯にまで突出していないケースもあります。
このように、しゃくれの特徴は「下顎の突出」です。噛み合わせの反対咬合に繋がることもあり、受け口と併発するケースもあります。
受け口の特徴
受け口は「反対咬合」、または「下顎前突」とも言われており、下の前歯が上の前歯より前方に位置する噛み合わせの状態です。
通常の噛み合わせとは逆に下の歯が前に出ているため、しゃくれと見間違えられることもありますが、受け口は歯並びの問題、しゃくれは顎の骨格の問題によるものです。
顎のしゃくれ・受け口になる原因
ここでは、受け口としゃくれの原因について挙げていきます。
しゃくれの原因
しゃくれは遺伝的な骨格の特徴によって生じることが多く、保護者がしゃくれている場合、お子様にもその特徴が現れる可能性が高いです。
また、口呼吸の習慣が顎の成長に影響を与え、下顎が前に突き出る形状を形成することもあります。顎の成長期に口呼吸が習慣化すると、しゃくれの骨格が形成されるため、早いうちから正しい呼吸習慣を身につけることが重要です。
受け口の原因
 受け口は遺伝、不十分な顎の成長、永久歯の生え方の問題、または無意識の癖などによって生じることがあります。下顎が上顎より大きい、または上顎の成長が不十分な場合、または乳歯から永久歯への移行がスムーズでない場合には、受け口が発生する可能性があります。
受け口は遺伝、不十分な顎の成長、永久歯の生え方の問題、または無意識の癖などによって生じることがあります。下顎が上顎より大きい、または上顎の成長が不十分な場合、または乳歯から永久歯への移行がスムーズでない場合には、受け口が発生する可能性があります。
さらに、以下の習慣により、受け口の形成に影響を与えることもあります。
- 指しゃぶり・指吸い
- 頬杖をつく
- 噛むときに顎を出す
- ポカン口
- 舌を噛む・舌で歯を触る
子供は、わざと顎を前に出す
(しゃくれる)癖がある?
1歳~2歳の間に受け口を心配する親御さんは多いのですが、この時期の子供はまだ顎の関節が柔らかく、顎を前に出す癖が見られることがあります。
しかし、この癖が必ずしも受け口に繋がるとは限りません。成長するにつれて顎の関節も発達すると、自然に改善することが多いため、無理に止めさせるのは逆効果です。そのため、過度な心配はせずに見守ってみましょう。
子供の顎のしゃくれ・受け口を
放置すると…
子供の反対咬合(受け口)を放置すると、心身の健康において様々な問題が生じやすくなります。
反対咬合はただの歯並びの問題ではなく、適切な治療を行わないと、長期的な健康への影響が懸念されるため、注意が必要です。
成長とともに悪化するため、見た目に影響する
小さいうちは軽度の反対咬合でも、成長に伴い悪化するリスクがあります。1~2歳までの歯並びは約半数が自然に改善しますが、3歳を過ぎても続く場合は治療が必要です。その場合は、歯科医師に相談することを推奨します。
顎関節症になりやすくなる
反対咬合は顎の関節に負担をかけ、顎関節症のリスクを増加させます。顎の痛み、開口障害、関節音などの症状が生じ、日常生活に支障をきたすリスクがあるため、早期のうちに対処しましょう。
活舌が悪くなる
反対咬合は舌の位置と口の閉じ方にも影響し、発音の問題を引き起こす可能性があります。特に「サ行」「タ行」が不明瞭になり、これがコンプレックスや日常生活への悪影響に繋がることがあります。
咀嚼機能が低下する
前歯で食べ物を噛み切ったり奥歯ですり潰したりするのが難しくなるため、咀嚼が上手くできず、消化不良を引き起こすリスクがあります。
大人になると治療が
難しくなる
子供の矯正治療では顎の成長を利用するため、装置だけで治療完了できることが多いです。しかし、成長期を過ぎた後の治療では、抜歯や手術など負担の大きい治療が必要になる可能性が高まります。
顎のしゃくれ・
受け口(反対咬合)の治療法
子供のしゃくれや受け口の治療は、成長中の顎・歯の状態に応じて行われます。そのため治療内容は大人のそれとは全く変わっていきます。子供の治療では、以下の方法が選択されます。
予防矯正(マイオブレース・
プレオルソ)
 予防矯正は、遺伝ではなく環境的要因による歯並びや噛み合わせの問題を改善する治療法です。幼少期から始めることで、お口周りの筋肉強化トレーニングと正しい生活習慣の指導、姿勢や口呼吸の改善などを通じて、将来の矯正治療の必要性を減らすことができます。
予防矯正は、遺伝ではなく環境的要因による歯並びや噛み合わせの問題を改善する治療法です。幼少期から始めることで、お口周りの筋肉強化トレーニングと正しい生活習慣の指導、姿勢や口呼吸の改善などを通じて、将来の矯正治療の必要性を減らすことができます。
取り外し可能なマウスピースを使用し、日中の1時間と就寝中、計12~14時間の装着が必要です。そして装着に慣れるまで、時間がかかる可能性があります。
当院で取り扱う矯正装置
拡大装置(床矯正)
 入れ歯に似たプラスチックの装置を用いて上下顎を拡げ、歯並びと噛み合わせを整える方法です。
入れ歯に似たプラスチックの装置を用いて上下顎を拡げ、歯並びと噛み合わせを整える方法です。
この治療は6歳から11歳の子供に特に有効で、永久歯のための適切なスペースを提供します。
インビザラインファースト(インビザラインティーン)
 小児矯正の分野において、かつては床矯正を通じて顎を拡大し歯並びを整える方法が主流でしたが、現在はインビザラインファーストのような透明マウスピースを用いた矯正が一般的になっています。
小児矯正の分野において、かつては床矯正を通じて顎を拡大し歯並びを整える方法が主流でしたが、現在はインビザラインファーストのような透明マウスピースを用いた矯正が一般的になっています。
このマウスピースは定期的に新しいものに交換され、食事や歯磨きの際には取り外すことができるため、口内を傷つける心配が少なく、虫歯のリスクも減少します。
治療対象年齢は6歳~10歳で、治療期間は約1年半~2年間です。
⭐︎第2大臼歯(12歳臼歯)が生え揃う、概ね12歳〜16歳以上くらいの方は二期矯正としてインビザラインティーン(インビザライン)での矯正治療を行うことができます。治療開始の時期は患者様それぞれの口腔内状況および成長段階に応じますので、当院までご相談下さい。